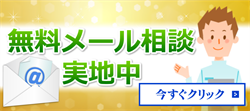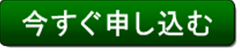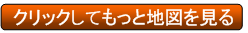歯周治療後3か月でHbA1cが0.43%低下。
・2022年に発表されたメタ解析では、2型糖尿病をもつ患者を対象にしたSRP単独の効果を算出する群と、非治療群を比較した20件のランダム化比較試験をもとに、歯周治療後3か月でHbA1cが0.43%低下したことが示されています。
これらのメタ解析のデータを根拠に、多くの歯周病および糖尿病関連の学会が、糖尿病をもつ患者に対する歯周治療を推奨しています。
・2型糖尿病をもつ患者に対する運動療法の効果を検討した代表的なメタ解析では、合計8538名を対象とする47件のランダム化比較試験が解析され、運動介入とHbA1cの変化との関連が検討されました。
その結果、毎週定められた時間を計画的に行う運動プログラムを実施した研究を統合したデータでは、運動群でHbA1cが平均0.67%低下していました。
さらに、運動総実施時間によって効果に差がみられ、週150分を超える運動プログラム(3か月継続)ではHbA1cが0.89%低下した一方で、週150分以下(3か月継続)では0.36%にとどまりました。
これは運動の強度や種類よりも持続的な総時間がHbA1cの低下に与える影響が大きい可能性を示唆しています。
そして、運動の種類別にみると、有酸素運動単独のHbA1cの低下は0.73%、レジリエンス運動単独では0.57%、両者の併用では0.51%といずれも有効性が確認されています。
(参考文献)
Simpson TC, Clarkson JE, Worthington HV, MacDonald L, Weldon JC, Needleman I, Iheozor-Ejiofor Z, Wild SH, Qureshi A, Walker A, Patel VA, Boyers D, Twigg J. Treatment of periodontitis for glycaemic contorol in people with diabetes mellitus. Cochrane Databese Syst Rev, 2022 Apr 14; 4 (4) : CD004714.
*****
2型糖尿病をもつ患者に対する歯周治療後3か月でHbA1cが0.43%低下に対して、同じく2型糖尿病をもつ患者に対する週150分を超える運動プログラムではHbA1cが0.89%低下という結果が得られました。
週150分を超える運動プログラムを3か月間継続した効果は、歯周治療後3か月後の再評価した際の効果のおよそ2倍ということになります。
2型糖尿病の傾向がある方は、運動に加え歯周治療も行う方がよいでしょう。
今回の報告では週150分未満かそれ以上かで分けて比較していますが、保存できない歯をインプラントに置き換え、咬めない状態が咬める状態になるとさらに長い時間の運動プログラムをこなせるようになるので、一層のHbA1cの低下を期待できます。
歯周病の既往がある高年齢患者の智歯を抜歯すると、41倍残存ポケットが生じやすい。
無症状の完全埋伏または半埋伏智歯を抜歯後の第二大臼歯を評価すると、遠心面の歯周ポケットとアタッチメントゲインは約2?改善していた。
術前に遠心のPDが4?以上であった第二大臼歯の73.6%は、6か月後の再評価時に4?未満に閉鎖した。
一方、年齢が高く(平均55歳)、術前により深い歯周ポケットがある場合、抜歯6か月後に4?以上残存する可能性が高かった。
さらに過去の既往がある患者では、これらの残存ポケットが生じるリスクは41倍高かった。
この結果は、智歯抜歯後に生じる欠損が、外科処置による歯周炎の影響を強く受けることを示す。
(参考文献)
Passarelli PC, Lajolo C, Pasquantonio G, Damato G, Docimo R, Verdugo F, DAddona A. Influence of mandibular third molar surgical extraction on the periodontal status of adjacent second molars. J Periodontol.2019 Aug ; 90(8) : 847-55.
*****
多くの患者で年齢が高まるほど歯周病リスクは上がる傾向にあるので、可能な限り若いうちに症状がなくても智歯は抜歯しておいた方が得策であるということが明らかになりました。
上顎前歯部に埋入した単独インプラントの切縁レベル変化の長期評価(5-19年の追跡調査)
1995-2010年に埋入されたインプラント3094本を対象としたが、すべての適格基準を満たしたのは113本(3.65%)であった。
最終的にこれら113本のインプラントのうち56本が対象となり、追跡調査を行った。
すべての症例において、初診時の写真、最終補綴装置時の写真、術後5-20年間の追跡調査時の撮影された。
全てのインプラントはNovel Proceraで最終補綴装置はメタルセラミッククラウンで修復された。
本件の対象患者は合計56名(56本のインプラント)、年齢幅:23-63歳、平均年齢:40.79±12.25歳、男性21名(37.05%)、女性は35名(62.5%)であった。
平均追跡調査期間は10.7±3.37年で、隣接歯とインプラントの切縁レベルの変化を認めたのは19.6%であった。
評価されたすべてのインプラントの残存率は100%であった。
インプラント上部構造と隣接歯との切縁レベルの変化は、11名の患者(19.64%)で観察され、そのうち2名は上部構造をやり替えることに興味を示したが、その他の患者においては評価期間を通して審美性の満足度は良好であった。
性別間の切縁レベルの変化については、男性(19%)と女性(20%)で統計学的に有意な差は認められなかった(P=0.238)。
年齢別の切縁レベルの変化の発生率は、20-30歳までの患者で41.7%、31-40歳までの患者で13.3%、41-50歳までの患者で23.7%、50歳以上のグループで6.3%であった。
異なる年齢グループ間には統計学的に有意な差は認められなかった(P=0.118)。
同様に、切縁レベルに変化が認められた症例とみられかった症例の各サブグループにおける臨床症例数を比較しても、統計学的有意な差は認められなかった(P=0.262)。
(参考文献)
Long-Term Assessment (5-19-Year Follow-up) of the Incisal-Level Changes in Single Implants Placed in the Anterior Maxilla : An Observational Clinical Study. Int J Oral Maxillofac Implants. 2025 Feb7 ; 40(1) : 33-40.
*****
上顎前歯単独インプラントで長期間維持された上部構造の切縁レベルの変化は、評価した成人患者症例の19.6%に認められたことが明らかになりました。
日本人における垂直性歯根破折の有病率および関連因子
垂直性歯根破折(VRF)は、深さ5ミリ以上の歯周ポケットの原因となりうる8つの病態(垂直性歯根破折、歯肉縁下う蝕、水平または斜走破折、限局性歯周炎、穿孔、歯根吸収、歯髄壊死または根尖性歯周炎)の中で最も多かった(32%、73/228歯)。
垂直性歯根破折の確認は抜歯(3歯)、外科的探索(5歯)および非外科的探索(65歯)にて行われた。
VRFは40代(37%)および女性(68.5%)に多く、歯種では下顎第一大臼歯(31.5%)、上顎小臼歯(19.2%)の順に高頻度であった。
多くは隣接歯が存在(87.7%)し、深さ8ミリ以上の歯周ポケットを有する歯(50.7%)、また、頬舌側に限局した狭い歯周ポケットを有する歯(78.1%)、クラウン装着歯(82.2%)およびポストを有しない歯(57.5%)に多い結果であった。
未根管治療歯にはVRFを認めなかった。
9つの因子のうち既根管治療歯、歯周ポケット(深さ)、歯周ポケット(広さと位置)、歯種、修復物、ポストの有無の6つの因子においてVRFと有意な関連を認めた(p<0.05)。
(参考文献)
Lee K, Ahlowalla M, Alfayete RP, Patel S, Foschi F, Prevalence of and Factors Associated with Vertical Root Fracture in a Japanese Population : An Observational Study on Teeth With isolated Periodontal Probing Depth. J Endod. 2023 Des ; 49(12) : 1617-24.
*****
既根管治療歯、歯周ポケット(深さ)、歯周ポケット(広さと位置)、歯種、修復物、ポストの有無の6つの因子においてVRFと有意な関連があることが明らかになりました。
下顎智歯抜歯ケースで0.35%に障害発生し、そのうち67%が半年後に完全回復。
2019年Cheungらは、約8年間に下歯槽神経障害を主訴として外来を訪れた4338件の下顎第三大臼歯の抜歯症例のうち0.35%に下歯槽神経障害が発生し、0.69%に舌神経障害が発生したと報告している。
なお、追跡調査した6か月間に下歯槽神経障害の67%、舌神経障害の72%が完全に回復したと報告している。
(参考文献)
Cheung LK, Leung YY, Chow LK, Wong MC, Chan EK, Fok YH. Incidence of neurosensory deficits and recovery after lower third molar surgery : a prospective clinical study of 4338 cases. Int J Oral Maxillofac Surg. 2010 Apr ; 39(4) : 320-6.
*****
8抜歯ケースで0.35%に障害発生し、そのうち67%が半年後に完全回復することが明らかになりました。
インプラントを智歯相当部位に埋入することはまれですが、仮にインプラント治療の際に同様な障害が発生した際も障害の完全回復するまでの割合や期間は参考資料と知っておいても良いと考えられます。
水平的GBRにより骨幅が平均約3.4ミリ獲得可能。
水平的GBRにより骨幅が平均約3.4ミリ獲得できることが報告された。
また、インプラント周囲に1.5ミリの骨幅が必要であることが分かっているため、インプラントのサイズを決定するための目安となるだろう。
(参考文献)
Naenni N, Lim HC, Papageorgiou SN, Hammerle CHF. Efficacy of lateral bone augmentation prior placement : A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol. 2019 Jun ; 46 Suppl 21 :287-306.
*****
GBRは垂直的よりも水平的の方が容易な印象がありましたが、水平的GBRにより骨幅が平均約3.4ミリ獲得できることが明らかにされていました。
歯科健診未受診の高齢者は死亡リスクが1.5倍になる。
・歯科健診未受診の高齢者は死亡リスクが1.5倍になることが分かった。
大阪公立大学と大阪大学の研究グループによるもの。
研究では、2017年10月から19年3月の間に継続して大阪府後期高齢者医療保険に加入していた75歳以上の94万6709人を対象に、歯科健診および歯科受診の有無と死亡の関連を解析・検討。
それぞれを「共にあり」 「健診あり・受診なし」 「健診なし・受診あり」 「共になし」に分類した。
その結果、「共になし」の高齢者が「健診あり、受診なし」の高齢者に比べて有意に死亡リスクが高く、男性で1.45倍、女性で1.52倍だったことが分かった。
(参考文献)
Journal of Gerontology Medical Sciences(5月7日)
カンジタ菌による虫歯にはフッ素の効果が低い。
・フッ化物がカンジタ菌による酸産生を抑制できない。
東北大学口腔性科学分野の?橋教授らの研究グループは、本来は酸素のある環境で増殖しやすいカンジタ菌は、酸素が存在しない環境でも酸を作り出し、歯を溶かす可能性があることを解明した。
研究グループは、カンジタ菌がどのように酸を産生し、フッ化物の影響を受けるかを5種類のカンジタ菌を用いて実験を行った。
その結果、カンジタ菌が酸素のない状態でも酸を産生することを発見し、その酸が歯を溶かす作用を持つことが確認された。
さらに、虫歯予防に広く使われているフッ化物が、カンジタ菌による酸産生を抑制できないことが明らかになった。
これはカンジタ菌がフッ化物に対して非常に高い耐性を持つことを示している。
(アポロニア21 2025年5月号 )
*****
『虫歯予防にはフッ素!』と古くからいわれてきましたが、今回の研究でカンジタ菌で虫歯ができること、フッ素の予防効果は低いことが明らかになりました。
男性6割、女性8割が「交際・結婚に影響」
交際・結婚を考えるのに、相手の歯並び・歯の色を気にする人は男性でおよそ6割、女性で8割。
婚活支援サービスを運営する(株)オミカレが会員1223人に対してWeb調査したもの。
交際・結婚を考える際に判断基準となるポイントについての質問(複数回答)で、男性の回答で最も多かったのは「体型」87.6%で、「体臭・口臭」は82.2%、「歯並び・歯の色」は61.0%だった。
女性で最も多かったのは「体臭・口臭」95.6%で、「歯並び・歯の色」は78.2%だった。
(アポロニア21 2025年4月号 )
*****
「収入」という要素が含まれていないので、交際相手・結婚相手の身体に関する特徴に関しての調査なのだと思います。
埋入深度が深すぎるとインプラント周囲炎リスクが8.5倍に!
両隣在歯のCEJより6ミリを超えて深く埋入されたインプラントは周囲炎の発症リスクが8.5倍になるということも文献的に示されている。
(参考文献)
Kumar PS, Enomoto H, Tsurumaki S, Ito K. Biologic height-width ration of the buccal supra-implant mucosa. Eur J Esthet Dent. 2006 Autumn ; 1(3) : 208-14.
*****
例えば、下顎第1大臼歯の繰り返しの根管治療および最終的には歯根破折で抜歯に至ったようなケースに対して、ショートインプラントで対応する場合、両隣在歯より深め埋入になる傾向にあります。
今回の研究で両隣在歯のCEJより6ミリを超えない方がよいことが明らかになりました。