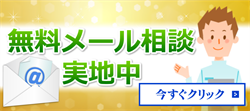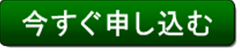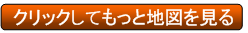インプラントと歯内療法の最近のブログ記事
埋入深度が深すぎるとインプラント周囲炎リスクが8.5倍に!
逆根管治療の術後の痛み予測は可能なのか?
逆根管治療後の術後疼痛の経過と、疼痛の予測因子に関する研究。
逆根管治療が行われた18-75歳の健康状態に問題のない173名について検討した。
術後5日間の疼痛を4段階で記録した。
痛みのレベルは、
0:痛みなし
1:軽度の痛み(鎮痛剤の服用を必要としない不快感)
2:中等度の痛み(鎮痛剤の服用でコントロールできる痛み)
3:強い痛み(鎮痛剤の服用で緩和されない痛み)とした。
平均疼痛レベルは1日目が最高で、その後徐々に減少した。
術後1日目で強い痛みはであった。
患者のほとんどは1日目、2日目に軽度あるいは中等度の痛み、3-5日目に痛みを最も多く記録していた。
5日目には86.5%の患者が痛みなし、または軽度の痛みであった。
強い痛みの予測因子を固定するため統計解析を行うと、性別、年齢、術前の骨の厚さに有意差を認めた。(P<0.05)。
術後の強い痛みの起こるオッズ比は女性患者が男性患者と比較して2.8倍増加、年齢が1歳上がると1.04倍現象、術前の骨の厚みが1ミリ増加するごとに1.4倍増加した。
(参考文献)
Malagise CJ, et al. Severe pain after endodontic surgery: an analysis of incidence and risk factors. J Endod 2021; 47 (3): 409-414.
*****
逆根管治療術後の強い痛みの起こるオッズ比は女性患者が男性患者と比較して2.8倍増加、年齢が1歳上がると1.04倍現象、術前の骨の厚みが1ミリ増加するごとに1.4倍増加することが明らかになりました。