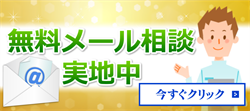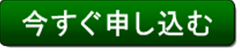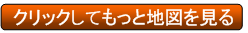インプラントと全身の健康の最近のブログ記事
歯科健診未受診の高齢者は死亡リスクが1.5倍になる。
・歯科健診未受診の高齢者は死亡リスクが1.5倍になることが分かった。
大阪公立大学と大阪大学の研究グループによるもの。
研究では、2017年10月から19年3月の間に継続して大阪府後期高齢者医療保険に加入していた75歳以上の94万6709人を対象に、歯科健診および歯科受診の有無と死亡の関連を解析・検討。
それぞれを「共にあり」 「健診あり・受診なし」 「健診なし・受診あり」 「共になし」に分類した。
その結果、「共になし」の高齢者が「健診あり、受診なし」の高齢者に比べて有意に死亡リスクが高く、男性で1.45倍、女性で1.52倍だったことが分かった。
(参考文献)
Journal of Gerontology Medical Sciences(5月7日)
カンジタ菌による虫歯にはフッ素の効果が低い。
・フッ化物がカンジタ菌による酸産生を抑制できない。
東北大学口腔性科学分野の?橋教授らの研究グループは、本来は酸素のある環境で増殖しやすいカンジタ菌は、酸素が存在しない環境でも酸を作り出し、歯を溶かす可能性があることを解明した。
研究グループは、カンジタ菌がどのように酸を産生し、フッ化物の影響を受けるかを5種類のカンジタ菌を用いて実験を行った。
その結果、カンジタ菌が酸素のない状態でも酸を産生することを発見し、その酸が歯を溶かす作用を持つことが確認された。
さらに、虫歯予防に広く使われているフッ化物が、カンジタ菌による酸産生を抑制できないことが明らかになった。
これはカンジタ菌がフッ化物に対して非常に高い耐性を持つことを示している。
(アポロニア21 2025年5月号 )
*****
『虫歯予防にはフッ素!』と古くからいわれてきましたが、今回の研究でカンジタ菌で虫歯ができること、フッ素の予防効果は低いことが明らかになりました。
男性6割、女性8割が「交際・結婚に影響」
交際・結婚を考えるのに、相手の歯並び・歯の色を気にする人は男性でおよそ6割、女性で8割。
婚活支援サービスを運営する(株)オミカレが会員1223人に対してWeb調査したもの。
交際・結婚を考える際に判断基準となるポイントについての質問(複数回答)で、男性の回答で最も多かったのは「体型」87.6%で、「体臭・口臭」は82.2%、「歯並び・歯の色」は61.0%だった。
女性で最も多かったのは「体臭・口臭」95.6%で、「歯並び・歯の色」は78.2%だった。
(アポロニア21 2025年4月号 )
*****
「収入」という要素が含まれていないので、交際相手・結婚相手の身体に関する特徴に関しての調査なのだと思います。
骨膜細胞から産出される、がん進行を抑えるTimp1とは?!
・腫瘍が骨に近接した浸潤前組織では骨膜の厚みが3-4倍に増加することを見出した。
腫瘍が近づくと骨膜の細胞からTimp1というタンパク質の分解を抑える分泌因子が産出され、これによりコラーゲンが蓄積することで骨膜が分厚くなり物理的にがんの進行を抑えること、Timp1遺伝子を破壊したマウスでは口腔がんの浸潤が顕著に増悪し早期に死に至ることを発見した。
(参考文献)
The periosteum provides a stromal defence against cancer invasion into the bone. Nakamura K, Tsukasaki M, et al. Nature. 2024. 634(8033) : 474-481.
*****
口底がん近接部位の骨膜肥厚の変化をがん浸潤の前後で比較したところ、健常部位に比較して腫瘍近接部位は統計学的に有意な差(P=0.0054)をもって厚みを増し、一度がんが浸潤してしまうと、統計学的な有意差(P<0.0001)をもって健常部位よりも骨膜厚さを減ずることが明らかになりました。
これにより、がん浸潤に生体が対抗するべく隣接する骨膜の細胞からTimp1というタンパク質の分解を抑える分泌因子が産出され、その結果骨膜の厚さが厚みを増すということになりました。
Timp1の量を何かしらの手法で増大可能であれば、がん浸潤を防ぎ、医学の進歩に寄与することでしょう。
歯が多いと余命が伸びることを確認。
東北大学の研究グループによると、歯が多いと認知症のない余命期間および全余命期間が伸びることが分かった。
研究では、日本老年学的評価研究の2010年の調査に回答した65歳以上の自立した男女4万4083人(平均年齢73.7歳、男性46.8%)を対象。
調査時とその後の10年間の追跡長データについて、歯の本数と認知症の発症、全死亡の発生との関連を調べた。
結果、モデルから推定された65歳時点での認知症のない平均余命期間は、男性で20本の歯を有する人で18.88年、0本の人で16.43年だった。
女性では20本の歯を有する人で17.12年、0本で14.40年だった。
65歳の時点での認知症の期間も含む全余命期間は、20本以上の歯がある人では、男性では17.81年、女性で22.03年、歯が0本の場合、男性で15.42年、女性で19.79年だった。
(参考文献)
Journal of the American Directors Association(9月11日)
*****
歯をすでに失っている人が余命を伸ばすためには、インプラント治療が有効であるということにもなりますね。
肥満・歯周病で認知機能が低下。
・広島大学の研究グループによると、肥満病態下における歯周病が、認知機能を低下させることが分かった。
健常マウス、肥満マウス、歯周病マウス、肥満・歯周病マウスのそれぞれに認知機能評価試験を行った結果、肥満・歯周病マウスのみ認知機能が顕著に低いことが分かった。
さらに、肥満・歯周病マウスにおいて、中枢神経系に分布する免疫細胞「ミクログリア」が有意に増加していることを確認。
ミクログリアは死細胞や病原体を捕食するが、活動が過剰になると神経炎症を引き起こすことが報告されている。
ミクログリアを枯渇させる物質を与えると、肥満・歯周病マウスの認知機能が改善した。
(参考文献)
Journal of Oral Microbiology (11月14日)
*****
肥満・歯周病マウスでは、ミクログリアが過剰な状態となり、神経炎症を引き起こすために、認知機能が低下することが明らかになりました。
咬筋の容積がサルコペニアに関連
咀嚼に重要な機能を有する咬筋の容積が低下することで、サルコペニアになるリスクが高まる可能性が示唆された。
同研究は今後、サルコペニア予防や早期診断として活用されると期待がかかっている。
順天堂大学の研究グループは、1484人を対象に、MRIを用いて咬筋容量を測定し、サルコペニア発症リスクとの関連性を調査した。
「文京ヘルススタディー」に参加した高齢者(男性603人、女性881人)を調査したところ、男性の咬筋容積の平均は35.3ml、女性は25.0mlだった。
また、咬筋容積が最も小さいグループは、最も大きいグループと比較して、サルコペニアのリスクが男性では6.6倍、女性では2.2倍も差があることが分かった。
特に咬筋容積は遺伝的要因やホルモンなどの影響を強く受ける一方で、四肢の筋肉量は年齢やBMIによる影響が大きかったという。
(参考文献:Achive of Medical Research 10月16日)
*****
咬筋容積が最も小さいグループは、最も大きいグループと比較して、サルコペニアのリスクが男性では6.6倍、女性では2.2倍も差があることが明感ありました。
インプラント治療でサルコペニアのリスクを減少させることができるのではなかろうかと推察しています。
高齢者の嚥下機能低下が睡眠の質に影響
睡眠の質は身体的要因と強く関連しており、誤嚥による咳も原因の一つとして報告されていることから、加齢による嚥下機能の低下は睡眠の質にかかわるといえる。
広島大学の研究グループによる、60歳以上の男女3058人(男1633人、平均年齢66.5±4.2歳)に対して自記式アンケートで調査した。
その結果、28.0%が嚥下障害を有し、19.1%に睡眠の質の低下が見られた。 嚥下障害と睡眠の関連を解析したところ、男性では嚥下障害のリスクがあることが、「睡眠の質が悪いこと」「睡眠不満足」「不規則な睡眠」と関連していた。
女性では、「睡眠の質が悪いこと」「睡眠持続時間6時間未満」と有意に関連していた一方で、「睡眠不満足」「不規則な睡眠」と有意な関連はなかった。
また、男女とも「睡眠の質」「入眠時間」「睡眠困難」「日中覚醒困難」と有意に関連していた。
(参考文献:Heliyon 5月31日)
*****
睡眠中は唾液はそもそもさほど分泌されないのでは?と思いますが、高齢者の場合ごくわずかな唾液が気管方向に流れ、誤嚥による咳が夜間に発生することはあり得ると考えられます。
咳をする以上、睡眠が分断されるので、結果として睡眠の質の低下するのでしょう。
子どもの夜更かしでミュータンス菌が増加
北医大らは、夜間の虫歯発生リスクの原因を突き止めるために、子供唾液を夕食後1時間おきに採取し、ミュータンス菌量を測定。
唾液採取は自宅で行ったのち、研究室まで郵送する流れとした。
その結果、重度の虫歯をもつ子供の唾液を解析すると、夜遅くなるほどミュータンス菌の量が増えていたことが分かった。
唾液中のミュータンス菌は夜遅くなるにつれて「増える子」と「増えない子」がおり、増える子供は重度虫歯に罹患するリスクが大きいとの結果を示した。
(参考文献:Jpurnal of Clinical Pediatric Dentistry 8月26日)
*****
重度の虫歯をもつ子供の唾液を解析すると、夜遅くなるほどミュータンス菌の量が増えていたことが明らかになりました。
小学校の歯科検診では、大半は虫歯が皆無の子供たちがいる一方で、少数の虫歯が多発している子どもがいると聞きます。
夜間は昼間よりも免疫が低下する傾向があるのかもしれませんね。
65歳以上の自立高齢者でも、16.4%が口腔機能低下症。
地域歯科診療所受診者(平均年齢51±16歳)の49.2%が口腔機能低下症と診断され、高齢期以前から口腔機能が複合的に低下していることも報告されている。
また、福岡県歯科診療所通院中の65歳以上の自立高齢者でも、16.4%が口腔機能低下症に該当し、残存歯数が19歯以下では該当者の割合が有意に高くなり、口腔機能低下症の該当の有無に関して残存歯数が有意に関連していたと報告されている。
この報告では、認知症や低栄養が認められない自立高齢者では、口腔機能低下症は加齢よりも残存歯数が関連要因となる可能性が示唆されている。
(参考文献)
伊輿田清美, 他.:地域歯科診療所における自立高齢者の口腔機能低下症に関する実態調査. 老年歯学, 34(3):406-414.2019.
*****
口腔機能低下症の該当の有無に関して残存歯数が有意に関連していることが明らかになりました。