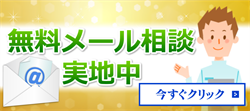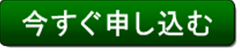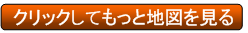歯周病で歯がぐらぐら
- 外食に出かけるのがおっくうに感じている
- ゴルフが趣味だが、飛距離が出ず悔しい思いをしている
- 丸のみをする癖があるのか、日々胃のムカムカが続いている
- ゴルフが趣味だが、後半のスコアが思うように上がらない
- いつも怒ったような顔をしていると言われたことがある
- 午前中は口臭がひどくて周囲の同僚が近付かない
- 最近前歯の突出感が増したような気がする
- 前歯に隙間ができてきた
- 根分岐部病変と骨隆起、アブフラクションの関係
- 重度歯周病患者では咀嚼によっても歯原性菌血症が生じる。
- B.forsythusが存在すると、歯周病の進行が7倍?!
- 歯周病で腸に異変?!
- なぜ歯周病は重度化するか?
- P.g.菌感染度で悪玉コレステロール値が上昇
- 歯根間距離が大きくなると、骨縁下欠損の頻度が高くなる。
- それでもタバコを吸いますか?
- 2型糖尿病と歯周病の関係
- 歯周病が悪化すると、口がネバネバするのにも意味があった。
- いわゆる"薬で治す歯周病治療"は免疫に悪影響。
- 受動喫煙で歯周病リスクが3倍に
- ピロリ菌で心臓病?!
- WHOも危惧する『薬で治す歯周病』
- 気象変化で慢性歯周炎が急性化。
- 口腔内では善玉菌なのに、血液中に入り込むと、心不全を惹起するリスクがあるストレプトコッカス・サングイニスとは?!
- 細菌がヒトのストレスを察知して、その病原性を高める!
- 歯周病の産生する酪酸が免疫に関係するT細胞を阻害する。
- 歯周病に抗菌薬を投与しても、6か月でその効果は消失する。
- 重度歯周病患者の口腔内でもレッドコンプレックスの割合は少ない。
- プロバイオティクスで歯周病予防?!
- インプラント周囲炎に歯周炎と同じ治療法を用いても奏功しない。
- 天然歯とインプラントを連結するなら、キーアンドキーウェイで固定が有効。
- 肺炎球菌に対するマクロライドの耐性菌はドイツ9.5%であるのに対して、日本は77.9%。
- 日本人の侵襲性歯周炎の原因菌は慢性歯周炎の原因と同じ。
- 非外科的治療は単根歯でも、歯周外科治療の2倍の時間がかかる。
- リグロスの効果はばらつきが大きい。
- 歯周病治療で肝硬変の症状改善か?
- P.gingivalisがもっとも病原性の高い歯周病菌なのか。
- 飲酒と歯周病リスク
- 歯周病でサルコペニアの病態悪化。
このようなことでお悩みの方
インプラントカウンセリングをお受けください
糖尿病治療で歯周病が改善
糖尿病治療が直接的に歯周病を改善することが分かった。
大阪大学の研究グループは、歯科的な介入は一切行わずに、29人の2型糖尿病患者に対し、2週間の入院下での糖尿病集中治療を実施し、治療前後の全身的な臨床指標や歯科的指標を解析した。
その結果、血糖コントロール指標に加え、歯周病の炎症程度を示すPISAが改善。
さらに、PISAの改善度の大小で被検者を2群に分けて比較解析したところ、大きく改善した群では糖尿病治療前のインスリン分泌能が有意に高値を示し、糖尿病性神経障害および抹消血管商家の指標も有意に良好な値となった。
(参考文献 Diabetes, Obesity and Metabolism 8月15日)
*****
歯科的な介入は一切行わずに、2型糖尿病患者に対し糖尿病集中治療を実施し、血糖コントロール指標に加え、歯周病の炎症程度を示すPISAが改善することが明らかになりました。
「歯周病」という言葉 20代の17%「知らない」
成人の約5割が、「この先、永久歯を抜く経験をする可能性がある」と感じている。サンスターグループが「いい歯の日(11月8日)」に合わせて実施した、歯周病に対する意識や口腔ケアに関する調査によるもの。
全国の20歳以上の男女1100人(20,30,40,50代、60歳以上の男女各110人ずつ)を対象に、7月7日にインターネットで実施した。
(アポロニア21 2023年1月号 )
歯周病はなぜ進行しても痛くない?
結論をいえば、ジンジバリス筋などが歯周病原菌が産生する酪酸が、神経突起を委縮させるためです。
歯周病原因菌は、発育が遅く病原性も弱いため、痛みの刺激によって生体の防御機構が作動すると排除されてしまいます。
そのため、酪酸によって痛みを遮断し防御機構から回避していると考えられます。
ある意味、歯周病原菌の生き残り戦略といえますが、酪酸が神経突起を委縮させているということ自体、神経に以外作用を及ぼすものだといえます。
腸管で善玉として働いている酪酸が、歯周組織だと悪玉になってしまうのでしょうか?
腸管と口腔との最大の違いは、腸管はムチンの保護層が700μmと圧倒的に厚いという点です。
口腔のムチンの保護層は0.3-1μm程度です。
口腔粘膜は重層扁平上皮でできており、表皮が一部破壊されても、その奥にも次の表皮細胞があるため重篤な状態にはなりません。
しかし、腸管では養分を吸収するため上皮細胞が1層だけ並んでいる単層円柱上皮でできています。
そのため、上皮細胞を保護する分厚いムチン層が必須なのです。
ムチン層に守られている腸管では、糞便中の酪酸はそのままでは粘膜に接することはなく、腸管粘膜細胞を活性化させる善玉の働きだけを続けることができます。
しかし、ムチンの分泌量は、精神的なストレスなどの外的要因で大きく左右されます。
何らかの理由でムチンの保護層が薄くなると、酪酸が粘膜と接してしまい、組織破壊が起こるのです。
ストレスでポリープができたという病態のメカニズムは、このように説明できます。
一方、ムチンの保護層の薄い口腔では、酪酸による組織破壊がダイレクトに進行し、歯周病を引き起こすことになります。
(アポロニア21 2022年2月号 )
*****
同じ酪酸であっても、存在する場所によってマイナスの影響を与えることがあることがわかりました。